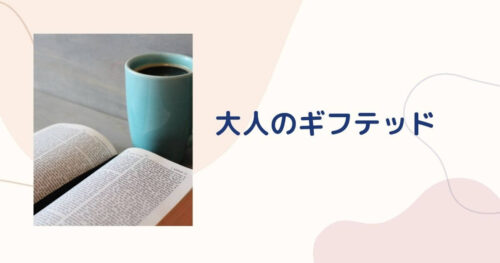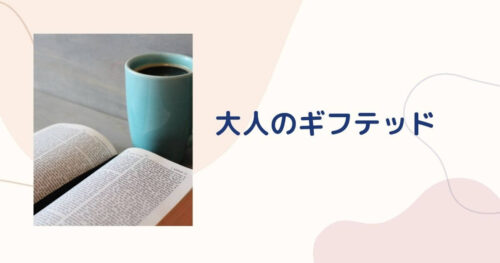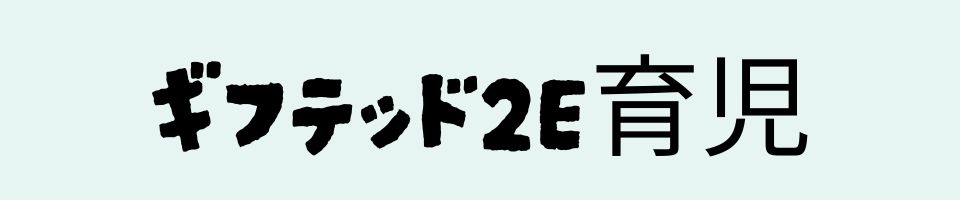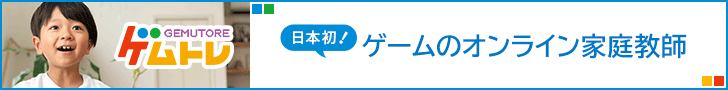ギフテッドの判定材料の一つに知能検査がありますが、行動特性も判断材料になることが多いギフテッド。
ここでは、一般的にギフテッドの特徴としてよく見られる行動の特徴を、息子の具体例とともに紹介していきます。
「わが子がギフティッドかもしれないと思ったら: 問題解決と飛躍のための実践的ガイド」によると、ギフテッドは共通して見られる行動特性があるとされています。ボリュームのある本ですが、この一冊を読めば大体ギフテッドのことは網羅できると言って良いほど詳しく書かれています。
タイトル通り「わが子」ではなくても、身近にギフテッドっぽい子がいる、もしくは教育関係者の方、学校の先生などにもおすすめの一冊です。
現在日本国内では、ギフテッドを認定したり診断するような機関は公にはありません。しかし、これから挙げる23の行動特性が複数見られる場合は、もしかしたらギフテッドかもしれません。ギフテッド児に共通してみられるこれらの行動特性はお子さんがギフテッドかどうか見抜く手立てになるでしょう。
具体例として息子の例を挙げていますが、女の子のギフテッドも当てはまる内容なので、ぜひ参考にしてみてください。
※ギフテッドといっても個々の特性は様々なので、あくまでもこちらに記載した例は息子の場合であり、当てはまらないケースもあります。
ギフテッドの定義と特徴を知りたい方は以下の記事も参考に↓
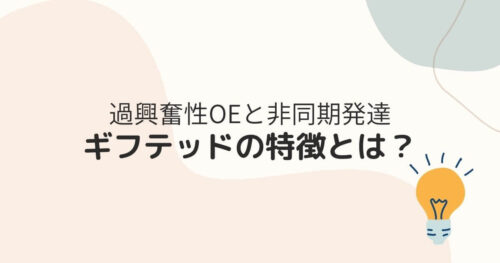
- 乳幼児から並外れた注意力がみられる
- 学習の呑み込みが早く、考えを素早く関連付けられまとめられる
- 多量の情報保持、優れた記憶力
- 年齢に対し並外れた豊富な語彙と複雑な文章構造をもつ
- 単語のニュアンスや比喩、隠喩、抽象的なアイディアへの高度な理解力がある
- 数字やパズルを好んで解く
- 未就学のうちにほぼ独学で読み書きのスキルを身につける
- 並外れた感情の深さ、激しい感情を持ったり反応をする
- 抽象的、複雑、論理的で洞察力のある思考
- 幼少期から理想主義や正義感がみられる
- 社会的、政治的問題や、不公正さや不公平さへ関心がある
- 長時間の注意持続、粘り強さ、高い集中力
- 自分の考えることで頭がいっぱいになる
- 自分や他者のできない状態や遅い状態にいたたまれなくなる
- 基本スキルをあまり練習せず素早く習得する
- 鋭い質問 教えられたこと以上のことをする
- 興味関心の幅が広い(ただし一つの分野への強い関心をみせることもある)
- 非常に発達した好奇心
- 試したり違う方法で行ったりすることに興味をもつ
- 通常使わないような方法で考えや物事をまとめる
- 特徴的なユーモアセンスがある
- ゲームや複雑な図式をとおして人や物事をしきりたがる
- 想像上の友達がいる(未就学児)
- まとめ
乳幼児から並外れた注意力がみられる
注意力(ある一つの事柄に心を集中し続ける力)が幼児期からみられます。好きになったらとことん突き詰め、時間も忘れ一つのことに没頭します。
息子の場合、興味関心の対象物は年齢によって変化していくものの、対象物の幅は多方面にわたっていました。とことん追求し底が見えたら興味対象の物が変わり、また突き詰めるといった感じです。幼少期から今でも変わりません。
ただし、あくまでも自分の興味のあること限定であり、興味のないことに関しては、むしろ注意散漫になります。
学習の呑み込みが早く、考えを素早く関連付けられまとめられる
ギフテッド児は、学習の呑み込みが早いという特徴があります。平均的な子に合わせて進む学校の授業が退屈に感じたり、焦ったく感じることがあります。
息子は小学2年生くらいから「学校」に疑問を持ち始めました。
授業が暇すぎて消しゴムが穴だらけになって帰ってきたり、鉛筆の削った木の部分を真っ黒に塗って帰ってきたり…。
小学校3年生の時、「僕はこの学校で学ぶことはもうないから学校をやめたい」とのこと。
先取学習などはしていませんでしたが、答えがすぐわかってしまうとついみんなの前で答えを言ってしまったり、矢継ぎ早に質問をしてしまって授業が止まってしまって毎日怒られてばかりで全然楽しくないからという理由でした。
ギフテッド児の中には、行き渋りが見られたり、不登校になる子も多いです。我が家は4年生のタイミングで学校を変えるという選択をとりました。ギフテッド児が不登校になる原因についてはこちら☟
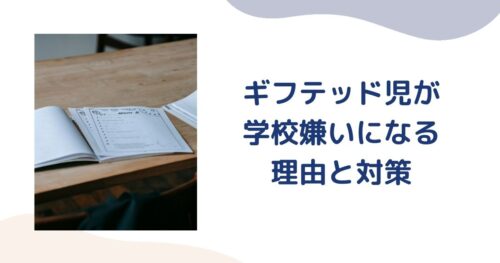
多量の情報保持、優れた記憶力
ギフテッド児は、同年代の子よりも、早く、簡単に習得します。また、「もっと知りたい」という知的欲求が高く、人よりも多くの知識を吸収します。
小さい頃から知識を得られるような本が大好きで幼児期は図鑑を隅から隅まで眺めていました。
2、3歳の頃は車全般が好きでした。車の名前はもちろん、絵本の隅にイラストとして書いてある道路標識も全て覚え、実際に道路で見つけると、「あれはこういう意味だね」と言っていました。
幼児期に昆虫に興味を持ち始めると、カブトムシ、クワガタに関しては、全てそれぞれの特徴を見分け図鑑丸々暗記していました。ギフテッドの男の子あるあるかもしれませんが、生息地の世界地図から地理も同時に覚えてしまったり、カタカナも読めるようになりました。
その流れで地理に興味を持ち、「しゃべる地球儀」を誕生日プレゼントにあげると短期間で国、首都の名前や国旗を一気に覚えてしまいました。
小学生になってからは友達との間でベイブレードが流行し、ベイブレードの購入した順や組み合わせも全て覚えていました。整理整頓は苦手ですが、足りないパーツや友達のパーツが紛れ込んでいたりするとすぐにわかるようでした。
このように生活の中で、記憶力の良さや、情報保持力について驚かされることが頻繁にありました。

また、一度通った道は記憶されるようで、初めての道でも帰り道迷うことはありません。
2歳4か月の頃、一度自転車で行ったプールの道を、後日タクシーで通ったときに「ここプールのとこでしょ?」と言ってきたことがありました。一度通った道を記憶している能力はギフテッドの人には珍しくないそうです。
見た映像が脳に残っており、再び通ったときにまたその記憶が蘇ってくるようで、カメラアイともいうようです。
4年生の時、旅先で一度しか通ったことのない道を、2回目に通ったときに車の窓から景色を見ながら

この道は〇〇に行くときに通った道だね。
というので、本人に聞いてみると全部景色が連続写真のように記憶されていくとのことでした。
年齢に対し並外れた豊富な語彙と複雑な文章構造をもつ
多くの子が、一般的な成長過程よりも数ヶ月早く話し始めます。また、本を読むことが好きな子が多いとも言われています。
知能テストのWISC-Ⅳ、いわゆるIQテストを9歳3か月の時に行ったのですが、息子は言語理解の部分が突出しており、IQ155以上、パーセンタイルでいうと99.9%以上との判定でした。これは1000人以上の中で一番という意味だそうで、子供用のWISC-Ⅳではこれ以上は測定不可とのことでした。
当時海外に住んでおり、日本のTVは繋いでおらず日本語の番組は見られない環境だったため、インターネットや本などから吸収しているものと考えられます。
喋り始めるのも周りより早く、小学校低学年くらいの頃は大人みたいな言い回しをするねとよく言われました。
このように高度な言語能力を持っているのは代表的なギフテッドの特徴です。
日記や作文を書くのは得意で、週末の日記何書こう?と一瞬悩みはしますが、文がまとめられないなどそういったことはなく、数分で書き上げていました。
ただその視点は面白く、仕上がった作文を読むと、こんな視点で見ていたの?!と一般的な視点とはちがうところから物事を見ていたりして面白いなと思うことがよくあります。
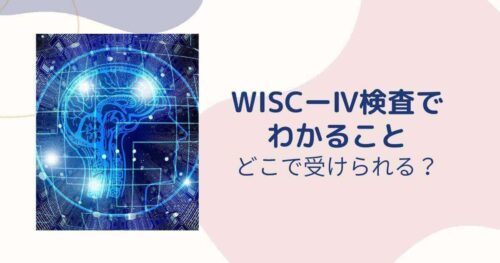
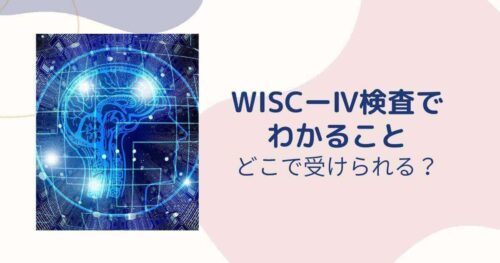
本に関しても、よく読む方だったと思います。
かいけつゾロリのシリーズや、「たのしい!科学のふしぎ なぜどうして?」(高橋書店)のシリーズが大好きでした。一年生から四年生までシリーズがあり、他にも「宇宙」「社会」「日本」「世界」「こころ」のシリーズもあります。これらの本は低学年のうちから擦り切れるほど何度も読み返していたので全て頭に入っています。
単語のニュアンスや比喩、隠喩、抽象的なアイディアへの高度な理解力がある
比喩や隠喩に関しては息子は苦手でした。意味を言葉のとおりに受け止めてしまうことがあります。
知能検査でも比喩表現の正解率が低かったようです。悪気もなく、言葉もストレートに発してしまうこともよくありました。「ママは顔にぶつぶつがあるけどかわいいよ」など、ぎょっとするようなことを言ってみたり、穴の開いている靴下を履いていて「随分おしゃれな靴下ね」というような表現をすると、そのまま受け取ってしまう。というようなことがあります。2Eの部分にも関係しているようです。
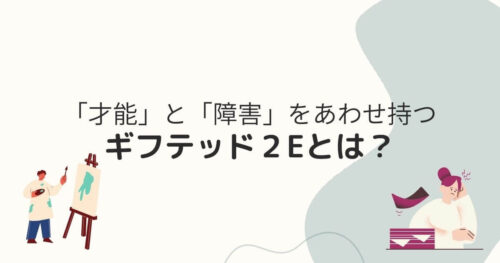
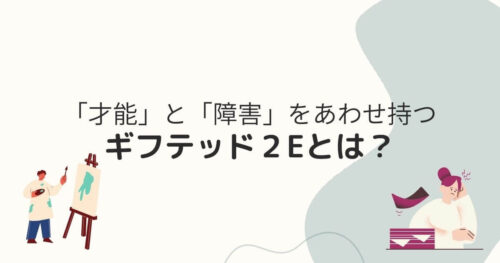
数字やパズルを好んで解く
ギフテッドの中には、数学が得意で小学生で高校生の内容を理解している子、算数オリンピックで優秀な成績を修めるお子さんもいらっしゃいます。
息子は算数は教科の中では一番得意ではありますが、そのタイプではありません。また、単純な計算ドリルや100ます計算などの繰り返し問題は好きではありません。しかし「宮本算数教室の賢くなるパズル」のような考えて数字をはめていくようなパズルは好きでした。
頭で考えることが好きなようです。
未就学のうちにほぼ独学で読み書きのスキルを身につける
文字に関しては教えていないのに気づいたら文字を書いていた、読んでいた、など独学で身に付けてしまう子もいます。
息子はさほど文字に興味はなかったのですが、幼稚園の年長さんのときにクワガタやカブトムシの種類の名前を知りたいという理由で読めるようになりました。一方、書くのは苦手です。綺麗に書こうと思えば書けるのですが、綺麗に書く意味が感じられないと綺麗には書きません。そのため、書写の授業以外は、ノートも殴り書きのように書くのでとても汚いです…。
「なぞらずにうまくなる子どものひらがな練習帳」は繰り返すのではなく、書き方のコツがイラストでわかりやす書いてあるので嫌がらずに取り組みました。
並外れた感情の深さ、激しい感情を持ったり反応をする
ギフテッド児のあらゆる根本に流れているのが突出した激しさだそうです。
書籍の中では、これが最も重要な特性であるとしており、ギフテッド児は全てのことに人一倍猛烈だと記載があります。まさに度を越えた性格にも見えると本にもありますが、息子もそうでした。
オセロ、ウノあたりは絶対勝ちたい!人生ゲームは毎回自分の人生に置き換えてやるので、借金まみれになったときはこの世の終わりかのように本気で泣いて悲しみ、一位でゴールできたときはあたかも本当にお金持ちになったかのように喜びます。
幼児期のみに見られるものなのかと思っていましたが、小学校高学年になっても激しさは変わりません。体育の授業でチームプレーの競技をして不本意にも負けてしまったときはものすごい剣幕で怒りながら帰宅します。
また、兄妹や親との衝突の時は、家の中だと他人の目もないので一番激しく感情をむき出しにします。相手が女の子だから、小さいから、といったような手加減は一切しません。口が達者なため、相手が親だろうが先生だろうが激しい口論になることも。
このように、ギフテッドの特性の部分で一番大変なのがこの激しさの部分だと言っても過言ではありません。
口撃だけならまだ良いのですが、某発達専門の医師の先生も「手が出たりするのは当たり前です」とのこと。親としてこれが一番頭を悩ませる問題でした。
この特性の項目で面白かったのは睡眠に関してでした。ギフテッド児は睡眠すら激しさを伴うとのこと。
まさに幼児期はロングスリーパー。お昼寝を1日4回したり、一度寝たら3時間は起きないような本当によく寝る子でした。
特にギフテッドの男児は猛烈に深く眠るため、夜驚症やおねしょにもなりやすいそうです。我が家も悩んで病院に行ったことがあります。
今は、年齢に対して睡眠時間は短いと思います。あんなによく寝ていたのがウソのように寝ないようになりました。
9歳ごろからショートスリーパーで就寝時間はだいたい23時前後です。小学生がこんな時間まで起きていてはダメなことはわかっているのですがこちらが声をかけても「じゃあ寝るか」とはなりません。


抽象的、複雑、論理的で洞察力のある思考
情報を処理する方法は「聴覚継次型」と「視覚空間型」があり、大抵の人がどちらかに偏っているとされています。得意とする処理方法によって抽象的思考か論理的思考か分かれます。
「聴覚継次型」の人は聴覚優位で言語能力が多く、論理的思考。順番に一つずつ取り組むのを好みます。
一方、「視覚空間型」の人は視覚優位で、抽象的な思考を好むとされています。同時にいくつもの課題を並行して取り組みます。
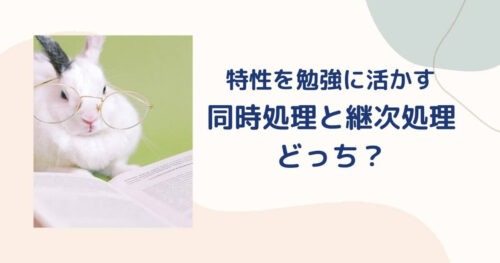
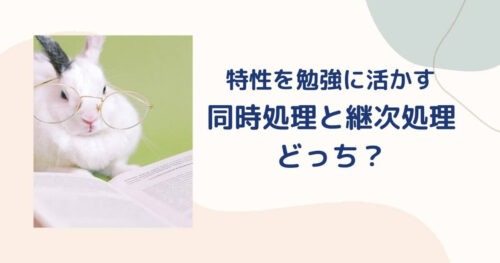
息子は、聴覚優位で論理的思考です。
例えば、本人が他人に説明するときも、こちらが説明するときも論理的な説明を好みます。
小さい頃は観察力があるな、よく見ているな、というように思っていましたが、洞察力がどうやら高いようです。普段から物事を多角的に見ていることが多く、本質もすぐに見抜きます。
誰がどういう性格か、先生がどういうタイプかなどは早い段階で見抜いたり、頭の回転も速いので、誰かがダラダラと話していたりすると、「つまり〇〇ということでしょ。」とすぐに話をまとめようとします。
幼少期から理想主義や正義感がみられる
ギフテッド児は自分や社会に対して理想主義が見られます。
息子の場合は、自分自身に高い目標を設定し、力が及ばないと、苛立ちとなって表すことがあります。自分の描く理想像が常にあり、それに向かってチャレンジしていきます。また、平凡な日々は退屈で、刺激を求めます。
当然失敗することも多いのですが、その失敗を生かし、改善し次につなげていきます。息子の場合は、失敗を恐れず、なんなら失敗しても楽観的にこういういい面もあったからまあいいよね!と開き直っていくので、よほどでないかぎりはリスクがあるからやめておこう。というような考えにはなりません。
正義感に関してはむしろ欠けていると思います。ルールも交通ルールくらいの法律レベルなら守りますが、20時半以降はピアノは弾いてはいけない、マンションは足音は静かにしないといけない、といったことは何百回も言いましたがピンときていないようで、基本的にはこれくらいいいだろう、と自分で判断してルールは破ります。
※追記(2024.9) 正義感に関しては、年齢とともに変化が見られました。


社会的、政治的問題や、不公正さや不公平さへ関心がある
政治問題はまだそこまで興味をもっているようには思いませんが、公平さは求める傾向にあります。ケーキの大きさがどっちが大きいから始まり、妹のほうが習い事を多くしていたり、自分が経験していないことを妹だけが経験していたり、そういったモノ以外の経験値なども公平さを主張します。
必ず自分が得をするようにならないとまた激しく怒ります。お兄ちゃんだから我慢、といったようなことは通じません。
長時間の注意持続、粘り強さ、高い集中力
集中力や粘り強さは乳幼児から成人ギフテッドまで見られる特徴です。
息子も幼児期から過集中はよく見られる特徴でした。工作をやり始めたらイメージしているものを作り上げるまで止まりません。本も読み始めたら一気に最後まで読み切らないと気が済まなかったり、勉強もやりはじめたら止まりません。
ただし、切り替えがとてつもなく下手なので、勉強に取り掛かるまでにものすごく時間を要します。小学生の頃は散々やりたいことをし終えてからではないと宿題に手を付けず、夜の22時頃勉強をし始め、そのまま23時過ぎまで止まらなくなり、力尽きて寝るような日もありました。一時期は「早く寝なさい」と声をかけていましたが、これも言うのをやめました。
読みたい本があれば眠かろうが最後まで読み切らないと気が済まないうえ、過集中モードに入ると私の声なんて一切聞こえていません。(これに関しては、耳は聞こえているのですが、一切反応をしないと言った方が正しいかもしれません。)
自分の考えることで頭がいっぱいになる
ギフテッド児は、激しさからしばしば物思いにふけったり、白昼夢を見たりすると言われています。
本人の頭の中をのぞいたことがないのではっきりは判断しかねますが、いつも色々なことを考えているな、とは感じます。ただし、息子の場合は、主には現実世界のことです。頭の中に思考が充満するような感じであればあてはまりますが、よくギフテッド児の特性にある、自分の世界に入って空想や想いにふけっている「白昼夢」というのはありません。
受験期の息子(当時11歳)が一緒に電車に乗っているときに「いつもいろんなことを考えている」と言っていたので、何を考えているのか聞いてみると「どうやって遊びの時間を捻出するかを考えている。」とのことでした・・
自分や他者のできない状態や遅い状態にいたたまれなくなる
完璧主義のギフテッドも多いとありますが、息子は幼少期の頃はそこまで完璧主義ではありません。いい加減なところもかなりあり、逆に私のほうが気になってしまうことも多々あります。
小学生の頃は、みんなで一つのものをやり遂げるような活動において、できない人がいるとイライラしていました。学校での劇の練習の際、自分は他のパートのセリフも間も覚えているのに、何度も失敗する子がいたようで怒って帰ってきたことがありました。自分と同等の能力を周りにも求めがちです。
ギフテッド児は、物事へのめり込む様子も強烈にのめり込みます。
他人との知識量との差にがっかりしたり、同じように短時間で習得できないのかいたたまれなくなることもありますが、成長とともにみんな学ぶ速度が違うこと、興味関心ごともそれぞれ違うことなどを学んでいきます。
基本スキルをあまり練習せず素早く習得する
ギフテッド児によく言われる特徴の一つに習得の早さがあります。例えば、算数で言うとステップを飛ばして頭の中で解き終わることも多いです。
また、勉強に限らず、何事もコツをつかむのがうまいなと思います。スポーツや楽器、ゲームさまざまな事柄において、練習時間は人より少ない時間と労力である程度のところまで習得します。
スポーツの例で言うと、東京オリンピックに感動し、突然テニスを始めました。家族でテニスをやる人はおらず誰も教えてあげられないので、まずはネットで調べ、自分で本を読み、知識を頭いっぱいに入れ、実際に色々試しながら独学で習得しました。
テニス教室に通い始めると3ヶ月で上級クラスに上がったり、大会の選抜メンバーに選ばれたりすることもあります。
補助輪なしの自転車、スケート、スケートボード、水泳、二重跳び、卓球など練習を少しすれば大体のことはすぐ人並みにはできるようになります。とはいえ、抜群に運動ができるタイプのギフテッドではありません。
また、iPadや電子機器の使いこなし方は目を見張るものがあります。最近の子だから、と言えばそうなのかもしれませんが、iPadに関しては小学生中学年頃からスクリーンタイムでいくら制限しても次々にすり抜けていくのでこちらがお手上げ状態です。
ピアノの練習も同様に、ハノンのような基本練習は大嫌いです。練習自体好きではなく、コンクールの前ですら練習はほとんどしません。もう仕上がっていたからなのか、練習は必要がないという本人なりの理由があり、コンクール前日まで丸一カ月練習もせず、レッスンも受けず本番のステージに立ちます。
前日に2回通して弾いただけですが特に緊張もせず堂々と演奏し予選は通過します。しかしコツコツ練習はしないので本選にはなかなか行けません。
鋭い質問 教えられたこと以上のことをする
大人も答えられないような質問をしばしばしてきます。空はなぜ青いの、なぜ夕焼けは赤くなるの、なぜ霧がかかるの、といった自然現象のことであればこっそり携帯で調べれば答えられるのですが、死んだらそのあとはどうなるのか、など答えに困る質問もよくされました。記憶力がいいところがあったのでいい加減なその場しのぎの答えはできませんでした。
小学生高学年の頃、バトルロワイアル系のゲームに一時期はまってしまったことがあったのですが、それは中毒性があるのでやめなさい、と注意したとします。すると、ではなぜ世の中にこのゲームが流行っているのか、なぜこんなゲームが売られているのにやってはいけないのか、といった質問をしてきます。
「ダメなものはダメ」というような言い方が最も通じず、ダメな理由を論理的に説明し、腑に落としていき、本人が納得する、という過程をいちいち取らないといけません。
ギフテッド児は大半の人とは全く異なるレンズを通して世の中を見ているので、本人が納得できるような理由が見当たらないと、一般的にはダメなことも納得しません。
アメリカは銃を持っていいのになぜ日本は持ってはいけないか。といったような質問もしてくるので、時には法律を出してきて説明しないと納得しないこともあります。
興味関心の幅が広い(ただし一つの分野への強い関心をみせることもある)
ギフテッド児は、興味関心があると、そのことに没頭します。
息子は興味関心のある事は広く深く、分野も多岐にわたります。幼児期はその時期によって一つの分野を掘り下げてから次へと変わっていくことが多かったのですが、現在は興味関心の幅はとても広いと感じます。いわゆる多趣味の人です。
あれもこれも全部やりたい願望があるにも関わらず、時間には限りがあるため、時間が足りなくなり睡眠時間を削り始めます。やりたいことが沢山ありすぎて24時間じゃ足りないから45時間くらいあればなあと9歳の頃言っていました。
非常に発達した好奇心
前述の項目と重なりますがこの特性もギフテッド児は顕著です。ギフテッド児を動かす原動力になっているものが、「好奇心」だと思っています。
幼児期からとにかく色々なことに興味があり、やってみたい!と思ったら、なんでもやってみるタイプでした。
お風呂に入ってなかなか出てこないので様子を見に行くと、タッパーにプロペラとモーターを付けて自作の船を作って浮かばせてみたり、新しく釣りのルアーを買えばルアーテストをしてみたり、思うような泳ぎ方でなければ発泡スチロールで自作したり。
家の中は、工作の道具、読みかけの本、ゲーム、勉強、などやりかけたものが散乱しており、周りからは散漫に見えるかもしれません。
試したり違う方法で行ったりすることに興味をもつ
なんでも分解するのが好きでした。ボールペンのばねの仕組みが気になったり、ばねがほしいので我が家にはばねだけ抜かれたボールペンが沢山あります。いい加減辞めて!というと、作れないかと針金を買って色んな太さの針金で自作のばねを作っていました。
ばねなんて伸びたり縮んだりするだけだろうと思っていましたが、圧縮ばね(押し縮めることで反発する力を利用するばね)と引張ばね(戻る力を利用するばね)があり、この引張ばねを見つけた時はとても興奮していましたが、私には全く興奮ポイントがわかりませんでした。
小学生高学年になると、ギアに興味があり、釣りのリールを分解していました。もちろんリールも自作します。レゴ、段ボール、など色々な材料で何種類も作っていました。最近レゴももう遊ばなくなったから友達にあげようと確認をしたところ、レゴのパーツのギアはほとんど別の工作の部品として使われており、ギアだけありませんでした。
音楽に関しても同じ曲を色々な調や楽器(ピアノ、電子ピアノ、エレクトーン)でアレンジするのも大好きです。ただし楽譜は読めません。クラシックも全て耳で聴いて覚えるので楽譜は後で確認する程度です。
音楽については実際のアレンジ動画付きでこちらの記事に記載しています。


通常使わないような方法で考えや物事をまとめる
一般的な考え方や方法以外で進めようとすることがあり、周りからは受け入れられにくいことがあります。
算数の例でいうと、解答にある模範の解き方を見ても、僕はこうではなく、こういうやり方でやった、というようなことがよくあります。
一つの問題を解くのに3通りのやり方が思いつくと、3通り全て試してみたくなるそうです。どれが一番早く正確に答えを出せるか考えるのが楽しいとのこと。
教科書にはないやり方で試してみたり、無駄を省くためにはどうしたらいいかを考えながら解いているようです。三年生の時の担任の先生には、他の子が思いつかないような考えを思いつくので、みんなもそういう考えもあるのかと、耳を傾けています、とおっしゃってくださいました。
特徴的なユーモアセンスがある
一番最初にボケたのは、2歳1か月頃でした。自分でボケてゲラゲラ笑っていました。
2歳の子にユーモアセンスがあるのかな?とその時は疑っていましたが、小さいころから人を楽しませたり笑わせるのが好きでした。度重なる転校で5校目ですが、行く先々で笑いをとれた!と帰ってくるのが学校に慣れてきたなと感じる目安です。今通っている学校の先生にも「〇〇さんが転入してから面白くて仕方ないよ」と言われたと言っていました。
ゲームや複雑な図式をとおして人や物事をしきりたがる
独自のルールを作って遊びを発展させていくようなことは多々ありますが、表立って人をしきったり、リーダー的な存在にはあまりなりません。ただ、何も遊具がない公園だとしても「〇〇君がいるとどんどん新しい遊びが始まるよね」とか、「〇〇くんがいると盛り上がるよね」と他のお母さんから言われることは多かったです。仕切っていると言えば仕切っているのかもしれません。
卓球にはまっていた時、公園でどうにか卓球ができないか考えて、「床卓球」というのを考えたと言っていました。
想像上の友達がいる(未就学児)
イマジナリーフレンドともいう、実際には目に見えない友達がいることがあるそうですが、これは全く息子の場合は当てはまりませんでした。
まとめ
これらの特性は、生まれ持った本質的な特性です。わが子がギフテッドであると気づくまでは、学校で浮かないように何とかしなければ!とあれこれ本を読み漁りました。しかし、発達のクリニックにかかり、知能検査を受け、医師にギフテッドかかもしれませんよと言われ育児の考え方を180度変えました。
まずは親である私がこの特性を受け入れ、尊重することが大切だと思っています。
「ギフテッド=天才、才能のある子、何でもできる子」というようなイメージがあるかもしれません。
しかし実際は特定の分野だけが優れていたり、感情のコントロールが難しかったり、周りの子とは感性が異なるため理解されなかったりと、本人自身が悩んでいるケースも少なくありません。
特に息子は「2E」であるため得意な事と苦手な事の差が大きく、本人自身が色々な葛藤を抱えて生きていることも知りました。ギフテッド児の抱える困難についても次回記していきます。
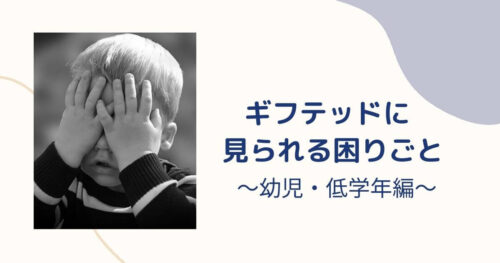
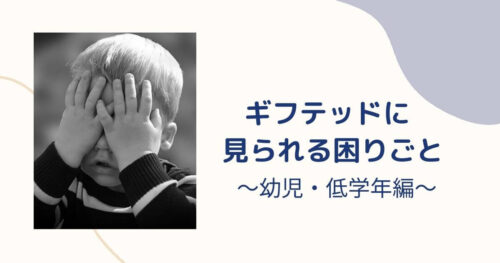
もしお子様が上記の項目に多く当てはまるのであれば、ギフテッドである可能性は高いそうです。
この本を訳書された角谷さんの書かれた本がこちら⇩
こちらは文庫本です。角谷さんの言葉でギフテッドについてわかりやすく書かれています。最近よく耳にするギフテッドって何?と思われた方、導入にピッタリの一冊です。
↓こちらはKindle unlimitedに登録すると無料で読むことができます。
月額¥980で200万冊以上の本が読み放題のサービスを利用した場合ですが、無料で読めるのでまずギフテッド教育についての知識を得たい方にはおすすめです。月額そんなに本を読まない方には30日の無料期間があるので、無料期間だけ加入することも可能です。登録後、管理画面で自動更新をオフにすることで、自動更新されることなく30日間利用できます。